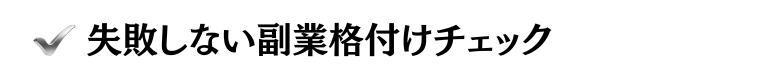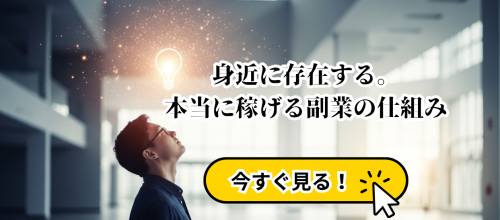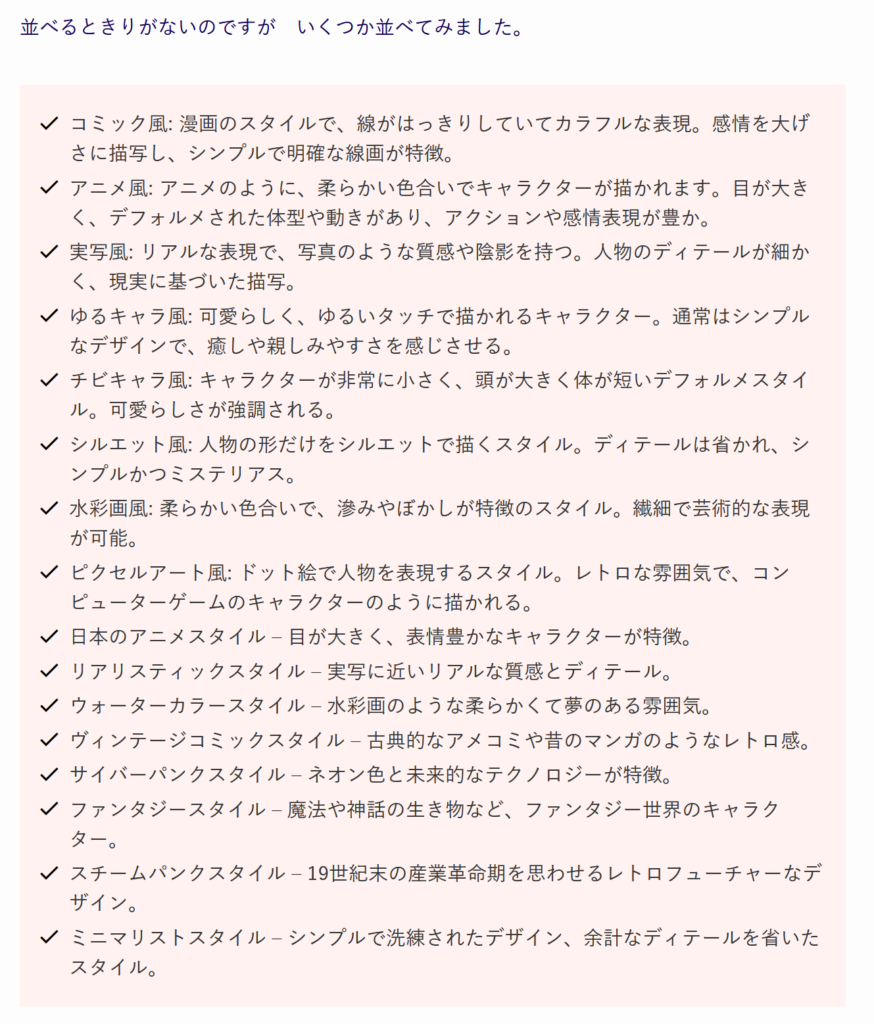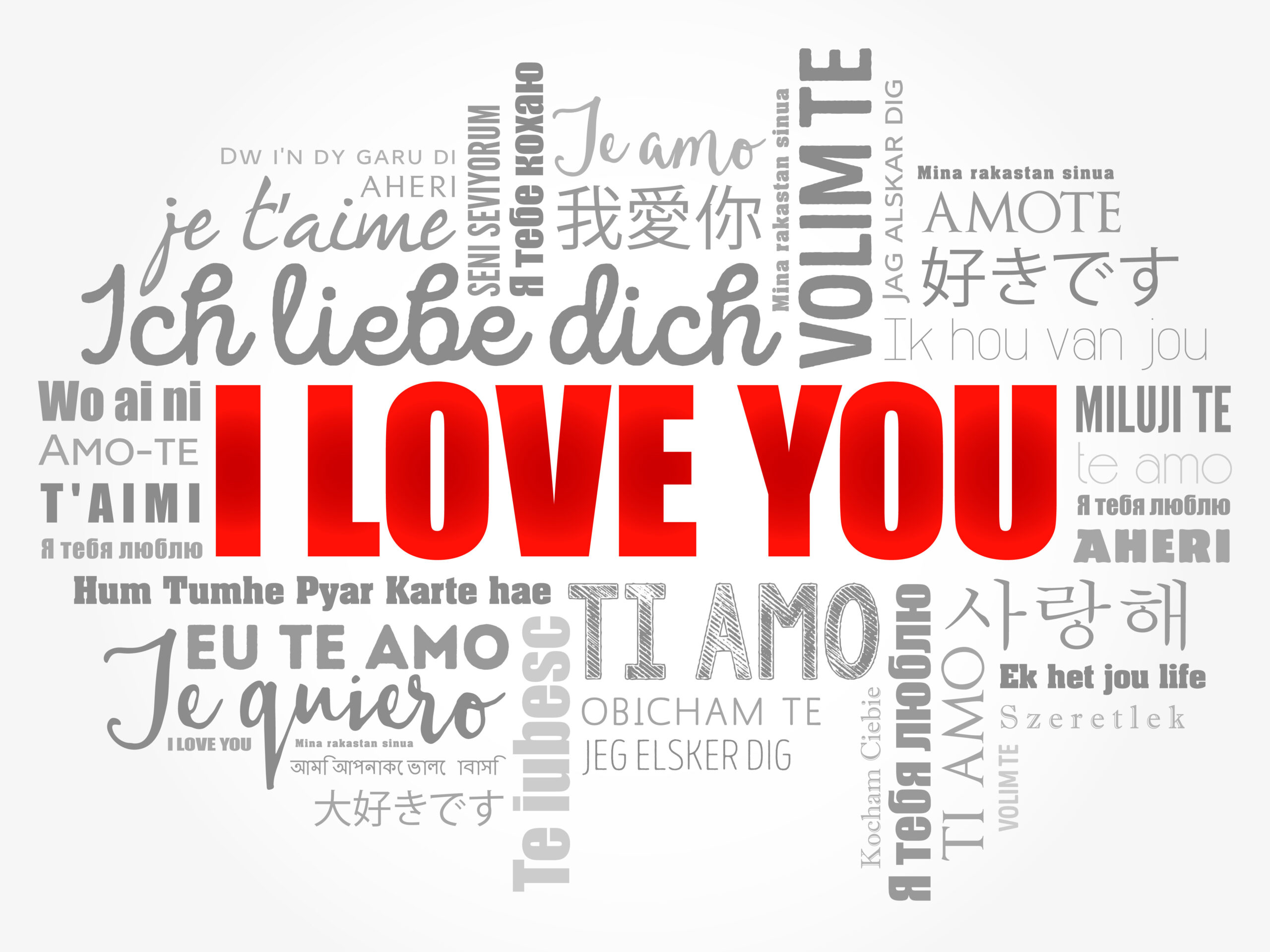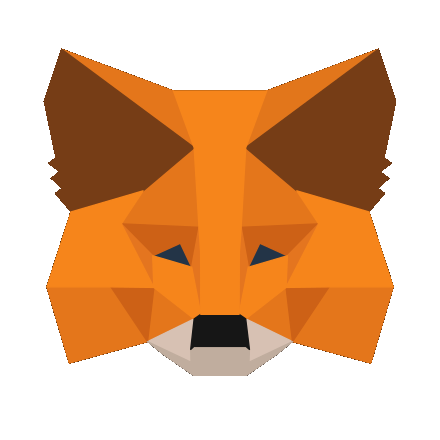最近になって、AI画像の生成技術が一気に身近になったことで、「副業としてAI画像を販売して稼げるんじゃないか?」と夢を抱く方が増えているように感じます。
実際、AIによる画像生成は以前と比べ物にならないほど進歩しており、自宅のパソコンやタブレットさえあれば、そこそこのクオリティの作品を短時間で作れる時代になりました。
しかも、SNSやストックフォトサイトではAI生成の作品が出回り始め、希少性の面でも従来の手描きイラストや写真とは異なる盛り上がりを見せています。
だけど、だからといって「誰でもゴロゴロ稼げるのか?」と問われれば、話は簡単ではありません。もちろん自分が作ったAI画像に付加価値をつけられれば、副業で一定の収益を得ることは不可能ではない。けれど同時に、あまりに多くの人がAI画像販売に参入し、そして無数の作品が溢れかえっている今、差別化をどう図るかが大きな課題になっているのも事実です。
これから副業としてAI画像販売を検討している初心者の方に向けて、「ゼロからどう始めるか」「どんな落とし穴があるのか」「それでもなお稼ぎ続けるためのヒントは何か」を僕なりの視点で整理してみたいと思います。この記事の最後には、すぐに行動に移したくなるようなゴールや、未来に繋がるヒントを示せればと考えています。
では、早速本題に入りましょう。
はじめにーAI画像副業の魅力と、想像以上に厳しい現実
こんな画像も無料で何枚でも生成できる時代になりました。

「AI画像を使った副業」は、2020年代の半ばあたりから一気に注目を集め始めました。きっかけの一つはStable DiffusionやMidjourneyなどの汎用AIによる革新的技術の登場です。これらの技術を使えば、従来は専門知識や優れた絵心が必要だったデジタルアートの領域にさえ、初心者が参入できるようになりました。
しかし一方で、同時期に多くの人が同じように「AIで画像を作って売ろう!」と考えたため、競争が激化しました。これが「AI画像は誰でも作れるので希少価値が下がり、単体販売では儲かりにくい」という現実を生む一因となっています。それでも、なぜこんなに多くの人がAI画像販売に惹かれるのか? そこには以下のような理由があると感じます。
- 初期投資の低さ
従来のカメラや撮影スタジオを用意するより費用がかからない。ペンタブがなくても開始可能。 - 時間と場所を選ばない
在宅で行えること、隙間時間でもサクッと画像生成・出品ができる手軽さ。 - 創造性を発揮できる
AI生成といえども、プロンプト(指示文)次第で世界観が大きく変わる。自分なりのオリジナリティを追求できる楽しさがある。
これらは確かに大きな魅力ですが、同時に立ちはだかる「量産されるがゆえの競争」「著作権やライセンスの問題」「収益化への長い道のり」といった現実も考慮しなければいけません。最初は「なんかすごく儲かりそう」と思って飛び込んでも、一枚も売れないまま撤退するケースは珍しくないのです。
AI画像を扱う前に押さえたい基礎知識 何がどう凄いのか?
AI画像の仕組みをかいつまんで言うと、「大量のデータ(画像・テキストなど)を学習し、そこから新しいパターンを生成する」ものです。人間の脳でいうところの記憶や知識の蓄積をAIモデルがデータセットとして持ち、それを再構成して新たなビジュアルを生み出します。
参考として画像生成この記事参考になりますよ
このようにプロンプト次第で様々な絵をAIが作れます。
例えばStable Diffusionはテキストプロンプトを受け取って、イメージを合成していく高度な手法を使っています。驚くべき点としては、以下のような特徴があります。
- 細部まで緻密に描画できる
最新モデルは高解像度画像でもある程度のクオリティを保てる。 - ユーザーの指示次第で多種多様なスタイルに対応可能
「油絵風」「アニメ風」「3Dレンダリング風」など、幅広いビジュアル表現が作れる。 - 学習データセットの広大さ
インターネット上の大量データを取り込み、膨大なパターンを持っている。
すごい技術だし、魔法のようにも見えますが、同時に誰でも手軽にアクセスできるとなると、自分が作った作品の希少性は下がってしまうのが実態です。
数年前に、こんな画像がコピペで作れる…となれば話は別ですが既に普通になっているんです。

これをどう活かしてビジネスに繋げるかが、副業初心者の腕の見せどころと言えるでしょう。
落とし穴①:「誰でも作れる」ゆえの大競争時代
AI画像販売の現場では、とにかく「作品数」が爆発的に増えています。ストックフォトサイトを覗くと、ほんの数年前までは手描きイラストや写真が中心だったコレクションに、AI生成画像が大量に流れ込みはじめました。そして、どれもそこそこ綺麗に仕上がっているのです。
問題なのは、写真や手描きイラストと異なり、作品のオリジナル性を担保するのが難しい点。AIツールを少しいじれば、同じテーマやスタイルの類似作品がいくらでも生み出せてしまいます。買う側からすれば、「わざわざお金を払わなくても、自分で生成すればいいじゃん」となるわけで、供給過剰が続くと価格はどんどん下がりがちです。
実際、AI画像のみを大量にアップして、月に数百円しか稼げない…という体験談も耳にします。単純に生成した画像をアップするだけでは差別化は難しい。ここをどう突破するかが最大のハードルだと言えます。
 小野寺
小野寺
ちなみに僕は、サブスクの画像生成サービスは全部解約しました。必要がなくなりました。
落とし穴②:著作権&ライセンスの複雑さ
もう一つ怖いのが、著作権をめぐる問題。
AIはデータセットから学習するため、元となる画像やイラストの類似部分を生成物に含んでしまう可能性がゼロではありません。
2025年現在も、AI生成画像に関する著作権の法整備はまだ追いついていない面があり、「どこからが侵害に当たるか」がグレーゾーンになりやすいのです。
さらに、販売プラットフォームによっては「AI生成物である場合は別途報告が必要」「第三者の著作権を侵害しない保証を提供せよ」などの制約がある場合があります。
軽い気持ちで画像をアップし、後から知的財産権トラブルに巻き込まれてしまうケースがないわけではありません。
- 著作権を管理するためのヒント
- AIツールの利用規約を読み込む。
- 生成した画像を逆画像検索でチェックする。
- 組み合わせた元データのライセンスを理解する。
こうした基本的な対策をしておかないと、最悪の場合、販売サイトからアカウント停止を受けたり、損害賠償問題に発展するリスクが出てくるので要注意です。
ブログやサイトで利用する部分には問題ないにしても、、販売となると規約を読まないと 色々な問題が発生する可能性があります。
でもまだ可能性はある:需要をつかむ“ひと工夫”
「結局もうAI画像は稼げないの?」と聞かれたら、僕は「単に画像を並べるだけでは難しいが、戦略次第ではチャンスはある」と答えます。
なぜなら、まだまだAI画像がすべてを網羅できていない領域や、手軽に生成しにくいジャンルもあるからです。
例えば、ビジネス用途に特化した「プレゼン資料向けの挿絵」「医療現場など専門業界に特化した図解」「和テイストを取り入れたユニークなイラスト」などは比較的ニーズがあるにもかかわらず、AIが苦手とする細かい設定や独特の世界観が要求されます。
また、単なる静止画ではなく、レイヤーや透過PNGなどの素材データとして扱いやすい形で提供するなど、「画像+α」の形で工夫すれば、その分高い値段で売れる可能性があるのです。
僕が以前に見た事例では、「AIで作ったキャラクターのバストアップイラスト」に加え、そのキャラクターの歩きモーションを数パターン作ってゲーム開発者向けに素材提供する、というビジネスを手がけている人がいました。
そうすると、単に画像一枚を売るのではなく「ゲーム素材パック」として売ることができ、数百円で売れるものが何十セットと売れていくわけです。
ここにユーザーを惹きつけるストーリーや設定資料を付け加えれば、さらにファンを獲得できるかもしれません。こうしたアイデアこそが「誰でも作れる時代」に必要な“ひと工夫”ではないでしょうか。
成功のヒント①:質より量ではなく、質×量を同時に追う思考
ストックフォト系の副業では、よく「たくさん投稿すればするほど売上が積み上がる」という話を聞きます。
確かに量は大切ですが、AI画像においては一枚一枚のクオリティやテーマの独自性も非常に重要です。なぜなら、量を増やしても類似作品が大量に作られやすいので、質を伴わない“量産”は埋没に繋がるからです。
僕の知り合いがストックフォトサイトにAI画像を出品していたとき、「とにかく数百枚を短期間にアップしたが、アクセス数が伸びなかった」と嘆いていました。
ところが、トレンド調査をしつつ、季節行事やビジネス資料向けの具体的なテーマに合わせた作品を意識して作ったところ、少しずつ売上が上がり始めたそうです。
つまり、本当の意味での“量”は、なんでもかんでも作るのではなく、“需要に即したテーマとクオリティ”を前提とした量でなければ意味がないのです。
- マーケティング視点の鍛え方
- 海外・国内のストックフォトサイトで人気のキーワードをリサーチする。
- SNSでユーザーがどんなビジュアルを好んでシェアしているか観察する。
- Googleトレンド等で季節やイベントごとの話題をチェックする。
こういったマーケティング目線でテーマを選び、質×量を両立することで、地道に売上を伸ばす戦略が必要になってきます。
成功のヒント②:プラットフォーム選び&セルフブランディング
実は同じ作品を出品していても、プラットフォームによって売れる価格帯やユーザー層が大きく異なることがあります。
ストックフォトサイト大手のShutterstockやAdobe Stockでは、常に世界中の人が素材を探しているためアクセスは多いですが、競合も多く、単価は抑えめになりがち。
一方、日本国内特化のサイトやPixiv FANBOXなど、コミュニティ色の強い場所では、作品のクオリティよりも作家性やオリジナリティが評価されることもある。つまり、自分の強みを活かせる売り場を探すのはとても大事です。
さらに、「自分自身のブランド」を確立していくことが長期的には効いてきます。
例えばSNSやブログを通じて、自分のAI画像の制作過程やコンセプトを発信し、ファンを育てるやり方です。
ただしここで一つ矛盾があって、「AI画像は誰でも作れるから、作家性を打ち出しづらい」という面もあります。
しかしそこを逆手に取り、プロンプトの工夫や独自設定を紹介したり、使用例や活用シーンを提案していくと、興味を惹かれる人もいるのです。
- セルフブランディングのポイント
- 作品に一貫したテーマや世界観をもたせる。
- 作業風景や生成ノウハウを部分的に公開する。
- 利用者の感想や実例をSNS・ブログで紹介する。
なお、プラットフォーム選びで困ったら、試しに複数に登録して出品してみるのも有効です。実績データを見ながら、売れるサイト・売れないサイトの傾向を掴み、徐々に出品先を絞るといいでしょう。
副業初心者でも見える光明と、これからのAI画像市場
ここまで、AI画像販売の魅力と厳しい現実、そして「落とし穴」「成功のヒント」について順番に見てきました。
実際のところ、AI画像は本当に誰でも生成できますし、似通った作品が量産されやすいので、そのままでは埋もれやすいのは確かです。
僕も以前、AI画像でひと儲けしようと踏み出した際、あまりの競争激しさに「これは思ったほど甘くないぞ」と冷や汗をかいた経験があります。
それでも今なお、AI画像の市場自体は拡大を続けており、ビジネスであれクリエイティブな活動であれ、新しいニーズがどんどん生まれています。
結局のところ、副業初心者がAI画像販売で成功するためには、以下のような要素をバランスよく押さえる必要があると感じています。
- 需要のあるテーマや用途を的確に狙う
- クオリティと量を同時に確保する努力
- 著作権やライセンス問題への知識と配慮
- 自分だけの付加価値やストーリーを添える
- プラットフォームやSNSでの存在感を高める
これらを心がければ、AI画像は十分に「副業として成り立つ可能性」があるし、もし売上が上がれば月に数千円から数万円規模の収入アップだって不可能ではありません。
もちろん、すぐに稼げるわけではないですし、参入者増加で単価が下がるリスクも高いので、長い目で見た戦略が大切です。
しかし、僕はこの「AI技術との共存」を楽しみながらやるのが一番いいと思っています。
僕が東京のクリエイターコミュニティで見た光景ですが、AI画像生成をする人同士が作品を見せ合い、互いのプロンプトを工夫し合って笑い合っている姿はとても活気に満ちていました。
人間の創造力とAIの演算能力が合わさると、お互いが刺激し合って新しい作品がどんどん生まれるのを目の当たりにすると、脳内に強烈な快楽物質が分泌されるような感覚さえ覚えます。そこには単なる「稼げるかどうか」以上の面白さがあるんですよね。
最後にまとめとして、「AI画像だけを量産して売る」だけでは厳しくても、AI画像+αのアイデアやプラットフォーム戦略、セルフブランディングなどをしっかり考えれば、まだ新参者にもチャンスは十分にあります。
そして一歩踏み出した先で、同じように挑戦している人たちとの繋がりができ、知識やノウハウが得られれば、今後の副業ライフにも大いに活きてくるでしょう。
もしもこの記事を読んで興味を感じたなら、まずは無料ツールやブラウザで使えるAI生成サービス(たとえばConoHaAICanvasConoHa AI CanvasConoHaAICanvasなど)で試しに何枚か作ってみるのはいかがでしょうか?
実際に手を動かすと、想像以上に奥が深く、きっと楽しくなると思います。そこから自分だけの独自世界を構築し、マーケットに挑んでみるのは、デジタル時代ならではの面白い副業の形ではないでしょうか。
僕自身、「え? AI画像販売なんてもう遅いんじゃないの?」と思った時期もありましたが、正確には「売り方次第でまだ十分に稼げる」というのが今の結論です。
落としどころとしては、ただ闇雲に生成して並べるだけでなく、どんな層にニーズがあるのかしっかり調べ、そして地道に数を増やしながら改善を繰り返す。
すると、いつの間にかちょっとした収入の柱に育っているかもしれません。
そして何より、これから先さらにAI技術が高度化すれば、画像の表現幅はもっと広がるはずです。
それに伴って新たな需要や市場が生まれる可能性も十分あります。副業初心者が今の段階でAI画像生成に触れておくことは、将来的にもきっと役立つはずです。
大きな野心を持つもよし、ちょっとしたお小遣い稼ぎの感覚で試すもよし。挑戦してみた先に、新しい未来の扉が見えてくるかもしれません。
この一連の流れを信じて実行していけば、あなたもAI画像で副業としての収益を得るだけでなく、次世代を見据えたスキルを身につけられます。
AI画像販売の世界は決して甘くはありませんが、挑戦する価値は大いにあると僕は思っています。どうか、この記事をきっかけに、自分なりのアイデアと熱意を重ね合わせて、歩みを進めてみてください。未来を切り拓くのは、いつだって「今、踏み出した一歩」から始まるのです👍
お薦めのAI画像生成プラットフォーム
有料から無料まで色々ありますがプロンプトさえ意識すれば ミッドジャーニ並みの画像が作れるのが、こちらの Googleのimagefxです。

無料なのにしっかりした画像を生成してくれます。
プロンプトは英語ですが非常に優れているのでお試しください^^